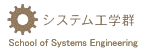
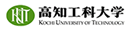
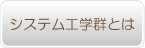
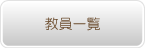
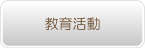
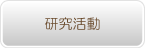
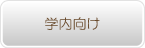
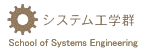
|
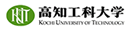
|
|||
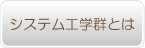 |
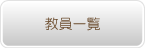 |
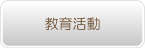 |
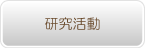 |
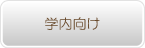 |
 |
| トップ > 「エネルギー工学専攻」新設 |

機械工学は、今、大きな転機を迎えています。ロボットに代表されるような「知能化」「システム化」「情報化」された次世代の機械の創出が求められているのです。こうした時代の要請に柔軟に対応し、人と環境に優しく、かつ高度に知能化された機械システム・生産技術や新製品を作り出すために、機械工学を核とした幅広い技術領域での研究開発を行うことができる先端的な専門能力を養います。
● メカトロニクス
現代の機械は従来の機械工学に加え、電気・電子工学の要素技術を組み合わせて作られるシステムです。ロボット、自動車を例にあげ、個々の要素技術がどのように応用・統合され、システムとして動作しているのかを具体的に学びます。
● 創造設計
機械や構造物を設計するには、設計の基礎である製図と機械要素の知識が必須です。これらの知識をもとに、具体的な機械や構造物の設計を経験し、設計力、製図力、判断力を身につけます。この講義では、図面作成、計算を実施し最終的にアセンブリの図面を完成させます。
従来の機械工学に軸足を置きつつ、メカトロニクスやコンピュータを利用した技術なども取り入れ、次世代のものづくりに貢献することをめざします。本専攻修了後は、自動車、ロボット、産業機械、医療機器の開発・設計はもちろん、化学から精密機械まで幅広い分野の製造業で生産システム構築・管理にあたる高度エンジニアとしても活躍できます。さらに、さまざまな機械を制御するために欠かせないプログラミングや人工知能の知識を生かし、ソフトウェア開発や鉄道、銀行などの大規模なシステムの運用といった分野で能力を発揮することも可能です。
現在、ほぼ全ての機械の知能化が加速的に進んできています。自動車を例に挙げると,前方の障害物を認識し自動でブレーキをかける自動車が既に市販され、将来は自動で目的地まで運転してくれるようになるでしょう。このような、未来の機械を産み出すためには、深い専門性に加えて、幅広い視野と知識が要求されます。システム工学群の専攻・副専攻カリキュラムを活用することで、これらの要求を十分に満足するエンジニアとして社会で活躍できる人材に育つことができます。

小惑星探査機「はやぶさ」の帰還や国産ジェット旅客機の開発などで注目を集める日本の航空宇宙産業は成長産業であり、増大する航空宇宙需要に対応するため多くのエンジニアを必要としています。本専攻では、機械工学や電子工学などの幅広い基礎知識を学んだ後、航空宇宙工学の各主要分野である構造、流体、推進、制御、宇宙計測の専門知識を身につけます。さらに知能機械工学や電子・光工学などを副専攻に選び、幅広い専門知識も習得します。
● 航空機構造工学
巡航、離陸、着陸時に要求される性能を満足するための航空機の概念設計手法を学び、自ら設定した乗客数と航続距離を満足する独創的なジェット旅客機の設計を行います。また、航空機の運動時に生じる荷重を計算する手法を学び、それに耐えうる翼および胴体の構造設計手法を学びます。
● 宇宙探査工学
宇宙の各領域について物理的知識を深めるとともに、探査機による直接計測やレーダー等、対象に応じた最適な計測方法や、衛星通信など機器の設計・搭載・運用の実際を学びます。具体的な計測例を交え、宇宙計測データの実際と問題点、極限環境下のものづくりのポイントについても議論します。
卒業後は、航空宇宙開発の専門機関や企業で航空宇宙機、同機器関連の開発・設計を行う技術者や研究者として活躍が期待されます。航空宇宙工学の技術は、高速鉄道車両の空力設計、先端軽量素材を用いたスポーツカーの構造設計、広範囲な気象観測システムなど多くの工学分野に転用されており、航空宇宙工学を学んだエンジニアは多くの工学分野での活躍が期待されています。
本専攻では、航空宇宙工学のエンジニアになるために必要な基本的知識の習得を目標とするので、航空宇宙機の機体設計に必要な知識は、実際の機体に関する話題を含んだ講義を通じて獲得できます。さらに,研究室配属後には、卒業研究として実際の機体開発に携わるチャンスがあります。

資源に乏しい日本のエネルギー問題、世界規模での長期的なエネルギー資源枯渇の課題を解決し、持続発展可能な社会を実現するには、エネルギー技術と共に、経済、環境、政策、ライフスタイルを含む幅広い複合分野の理解が必要です。エネルギー工学専攻では、機械・電気・建設の基盤工学分野を融合体系化し幅広くエネルギー技術を学び、次世代エネルギーシステム構築、システム効率化による省エネ技術、エネルギーマネージメントに活躍する技術者をめざします。
● エネルギー資源工学
エネルギーの形態やエネルギー資源、エネルギーシステムを学び、エネルギー問題と地球環境問題の現状と将来について学びます。
● 電気機器
化石燃料や原子力に替え、太陽光や風力、水力、地熱、波力、バイオマス等の再生可能エネルギーを有効利用する新エネルギー技術が期待され、これら発電技術を学びます。電気自動車やハイブリッド自動車等動力、電力の変換効率を改善する省エネルギー技術について学びます。
● 建築環境計画
建築や住宅での室内環境と省エネルギーの両立について、指標・規格・基準を理解し、具体的な室内環境形成技術と省エネルギーに関する計算方法を学びます。省エネルギー技術について近年の動向を理解し、室内環境と省エネルギー性に配慮した建築計画を作成して発表します。
エネルギーを取出して活用する仕組みを理解した技術者、エネルギー・エコ技術開発を担う技術者としての活躍が期待されます。プラント、インフラ、電力、重電、重工の分野、環境計量、省エネ設計建築などのエネルギー課題解決を必要とする分野において、本専攻で学んだエネルギー関連の専門知識を生かして、専門分野で活躍することが期待されます。
持続発展可能社会の実現には、エネルギー資源開発やシステム効率化による省エネ技術開発などと共に、エネルギーを理解し、エネルギーを効率的に利用しよりよく生きる新しい価値観の育成が重要と考えます。私達は、ものづくりの基盤となる機械・電気・建設分野をシステムとして融合することで、エネルギー分野の課題解決に取り組み、まずここ高知で、エネルギー教育・研究を通じた、地域の持続発展可能社会モデルの実現をめざします。

皆さんの生活で使っている家電製品、スマートフォン、パソコン、情報通信機器、LEDなどには「電気電子と光」に関する技術が使われています。この技術が無いと現代社会は成立しないほどです。電気電子と光の関係は切っても切れない関係。物質の根源は電子の流れからできていて、電気も電子の流れからできています。電気の流れは電場・磁場や光を発生させます。この専攻では、電気電子と光を扱える技術のエキスパートになるための勉強をします。
● 電気回路
皆さんが使っているスマートフォンやゲーム機は電子・光工学技術で動作しているといっても過言ではありません。本講義はその中で電子工学の基礎となる回路理論を基礎から応用まで詳細かつ幅広く学び、集積回路や電子制御回路が計できるようになることをめざします。
● 光デバイス
電磁気学、量子力学、半導体光物性などの基礎的知識を習得したのち、省エネで長寿命なLEDや記憶媒体、光ファイバ通信には欠かせない半導体レーザなど高度情報化社会の根幹をなす光デバイスを中心に光エレクトロニクス技術を学びます。
就職先には、電気メーカ、電力メーカ、産業機器メーカ、製造業機、通信などさまざまな職種の回路設計や保守メンテナンス等があります。日本だけでなく世界を支える技術です。大学院に進学すれば、さらに幅広い分野を勉強し、高度な技術を身につけると、より高度な技術者として就職でき、研究開発などの第一線で働けるようになります。近年の開発現場では、世界視野で幅広い知識と問題解決能力が求められます。社内公用語を英語にする企業も出てきています。勉強すれば世界中で仕事ができる技術者になれるのです。
知ってますか? スマートフォンや家電製品に半導体がたくさん使われてます。半導体は「産業界のお米」と呼ばれ重要な存在です。半導体技術者には電気電子と光に加えて、機械・エネルギー・構造設計など他の技術も必要です。システム工学群ではこれらは副専攻として学ぶことができます。そのような幅広い技術を習得して世界中で活躍している先輩たちもたくさんいます。みなさんも是非、勉強して世界で活躍する技術者になってください。

「安全・安心,そして心豊かな未来社会の創造」をめざす建設系の専攻です。意匠設計や構造設計を学び、ソフト・ハード両面から人々が快適に暮らすための建築や環境・生活のシステムをデザインできる人材を養成します。当専攻では、建築と土木の両方を学ぶことができます。社会が複雑化している今、求められているのは建築と土木を一体的に学び、さらに都市工学や環境学などの知識も身につけた総合的人材です。
● 建築スタジオ演習
主に実施設計を前提とする一般の設計協議への参加を通じて、より実践的な課題に対して空間を構想し、建築的想像力を発揮する力を養います。設計協議のテーマに対して適切な図面を作成したり、各段階で自らの考えをプレゼンテーションできるようにします。
● 防災システム計画
防災まちづくりの観点から、地震のメカニズム、都市の安全性の評価、都市防災システム計画の最新技術のほか、地震防災上の地理情報システムなどの都市防災技術を学びます。既存の建築物の耐震診断演習を通じて、建物の耐震性能および補修技術を習得します。
卒業後の進路としては、国内外で社会基盤整備に取り組んでいる土木・建築系の企業に加え、公務員、まちづくりや地域おこしをめざすNPO・NGOなどが挙げられます。リモートセンシングやGIS(地理情報システム)の専門知識を生かし、防災分野で活躍することも期待されます。また、プロジェクトマネジメントの知識を生かし、一般企業で企画や経営部門のマネジメントスタッフとして力を発揮することも可能です。
建築・都市デザイン専攻の教員は、それぞれ世界最先端の技術や実績を持ったプロフェッショナルが揃っています。世界に広がるネットワークを生かし、学生たちに国際会議への参加・研究発表、海外での研究活動や留学などの機会を数多く提供しています。さらに建築・都市デザイン専攻では、実社会での実践の場を数多く用意しています。学生の設計がコンペで採用され、実際の建物としてカタチになることも珍しくありません。
 |
| Copyright © since 2009 by School of Systems Engineering. All rights reserved. |